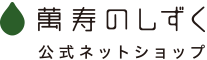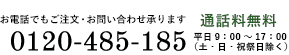特集
沖縄の心をうたう 琉歌の世界
日本に「和歌」があるように、かつて琉球王国だった沖縄には、「琉歌」と呼ばれる抒情歌があります。沖縄の美しい風景と、そこで育まれた素朴な心を、八八八六音の島言葉で綾なす情緒溢れる世界。代表的な琉歌の中から、桜、名勝、季節の歌と、琉歌をやさしく紐解くコラムをお楽しみください。

訳:流れる水に浮く桜の花が あまりにも美しいので 手にすくって眺めてみました

琉球を代表する歌人の一人、吉屋チルーの作。那覇の遊女であったチルーは、その美しさと歌の才能で、琉球王府のある首里までその名が届いていたそう。この句は、後に恋仲となる侍と出会った際に歌ったもので、チルーが上句を詠み、侍が下句を返したとも言われています。
下向きに咲く寒緋桜の美しさと儚さが、始まろうとする恋の喜びと共に、決して叶うことのないその行方を暗示しているかのようです。

訳:深く入り込んだ美しい浦はたくさんあるけれど その中でも名護湾が最も深く入り込んでいて美しい それにも増して素晴らしいのは、名護の娘たちの情け深さだ

沖縄本島北部にある名護湾の美しさを歌い上げたこの歌は、「本部ナークニー」という民謡の一節。昔の人たちが親しんだ海岸線はすでに埋め立てられていますが、この情景が詠われた国道沿いの公園に歌碑が建てられています。海の深さと情けの深さをかけた南国らしいこの歌の元歌は、奄美・加計呂麻島の「諸鈍長浜節」で、声に出して読むと、八八八六の流れるような言葉のリズムに深い情緒が感じられます。

訳:久米の五枝の松は下枝を枕にしているが 愛しい人は私の腕を枕にして寝ている

久米島の名勝「五枝の松」は、種類が多い松の中でも枝振りが美しいと言われる琉球松の名木。
地面に這うようにして横四方に広がる樹齢250年余りの枝の様を、人の腕枕に例えて讃えています。下句の「思童」は愛らしい子どもを、「無蔵」は男性が親しみを込めて女性を呼ぶときの言葉で、二つが合わさると「愛しい彼女」をさします。読み人知らずのこの歌は、「久米のはんた前節」の一節として、今も歌い継がれています。

訳:冬の夜の空を月に向かって鳴いて渡る 浦の千鳥の声を聞くのは寂しいものだ

琉歌で最もよく詠まれる季節は春、続いて秋で、冬は最も少ないそうですが、越冬のために飛来する渡り鳥は、沖縄の冬の風物詩です。中でも、島の言葉で「ちじゅやー」と呼ばれる千鳥は古謡にもよく歌われ、北風が吹く冬の浜辺でか細く鳴くその声は、なんともいえない寂しさを感じさせます。

訳:伊集の木の花はあのように清らかに咲いている 私も伊集の花のように
真白い花を咲かせたい

沖縄本島の最北端、国頭村に伝わる「辺野喜節」の一節。世界自然遺産、やんばるの森に自生する伊集はツバキ科の高木で、毎年5月頃、枝に連なるようにして白い花を咲かせます。この歌は、香り高く清らかな伊集の花の美しさを讃えつつ、「私もこのように咲いてみたい」という女心を詠ったものです。
やさしい 琉歌入門
ウチナーグチ(沖縄方言)と古語という、普段使わない言葉が重なるために「むずかしい」と思われがちな琉歌ですが、基本がわかれば大丈夫。琉歌の基礎をやさしくお教えします。
八八八六のリズム

訳:ホウセンカの花は爪先に染めて親の言うことは心に染めなさい
沖縄を代表する民謡である「てぃんさぐぬ花」も、実は八八八六です
琉歌は、沖縄の方言で歌われる伝統的な歌謡。わかりやすい特徴としてリズムの違いがあり、和歌(短歌)が「五七五・七七」の計31音で詠まれるのに対して、琉歌は「サンパチロク」とも呼ばれる「八八・八六」の計30音のリズムで詠まれます。
上句の「八八」で目の前の風景や状況を歌い、下句の「八六」では、上句についての心情を歌い上げる形式が一般的です。
琉歌は歌うもの
和歌と琉歌の最大の違い、それは、琉歌は歌謡、つまり「歌うもの」だということ。琉歌は単に読み上げるだけでなく、三線の伴奏に合わせて、喜怒哀楽を表現しながら歌うのが一般的で、奄美諸島では「島歌」とも呼ばれています。現代においても、沖縄の民謡や童謡、琉球舞踊や組踊で演奏される古謡の中で、琉歌は脈々と息づいています。

組踊の舞台では、台詞回しにも琉歌の「八八八六」のリズムが用いられています
二人の女流歌人
首里で生まれ、その後、沖縄各地で自然発生的に詠まれるようになった琉歌の作者層は幅広く、身分や性別、年齢を問いません。中でも、琉歌の名人としてよく知られているのは、18世紀に多くの琉歌を残した2人の女流歌人です。
そのうちの一人、吉屋チルー(チルーとは鶴という意味。よしや鶴、とも記されています)は、当時「ジュリ」と呼ばれていた那覇の遊女で、18歳で早逝した悲運の歌人。代表作の一つである『うらむひじゃばし比謝橋や 情け無いぬ人の 我身渡さと思て 架けて置きやら』(意味:恨めしい比謝橋は、情けのない人が私を渡そうと思って架けて置いたのだろうか)は、故郷を後にして遊郭に売られていく途中、深い川に架けられた橋を渡る時の不安と恨みを込めて詠われた歌と言われています。
もう一人、チルーと同じく農民の娘であったうんな恩納ナビーは、身分の低い農民ならではの心情や、情熱的な恋愛を自由奔放に、力強く詠った天才歌人として知られています。
沖縄を代表する観光名所、万座毛の入り口には、『波の声もとまれ 風の声もとまれ 首里天がなし 美御機拝ま』(意味:波の音も静まれ 風の音も静かになれ、国王様のお顔をみんなで拝みましょう)というナビーの歌碑が飾られています。

読谷村と嘉手納町との境にある比謝川大橋のたもとに、吉屋チルーの歌碑がひっそりと佇んでいます

恩納村のご当地キャラ
「恩納ナビーちゃん」としても親しまれている、沖縄を代表する歌人

万座毛の入り口に建つ恩納ナビーの歌碑
この地でのびのびと詠まれた情景が浮かんでくるようです
現代も人気です
短歌や俳句と同じように、現代の沖縄でも、琉歌は愛好家によって盛んに歌われ続けています。恩納ナビーの故郷である恩納村では、毎年、テーマを設けて作品を募集する「琉歌大賞」を開催しており、2024年で34回を数えています。ウチナーグチ(沖縄方言)にとらわれずに、現代の言葉で自由に詠われる琉歌のリズムは、これからも沖縄の人たちの心に響いていくことでしょう。
琉歌は心のビタミン
沖縄本島北部、名護市にお住まいの上原仁吉さんは、50代から琉歌を詠み始めて30余年。
「琉歌 伊集の会」の仲間たちとの歌会も楽しまれている上原さんに、琉歌の魅力についてお聞きしました。
日々の思いを記録する楽しみ
上原さんが琉歌を詠み始めたきっかけは51歳の時。当時の勤務先で「何かめでたいことがあると、みんなでお茶菓子を持ち寄って集まって、誰からともなく手を挙げて琉歌を詠む慣習がありました。それを真似して素人なりに詠んだのが始まり」だそう。それから自己流で勉強し、毎年、ご自宅の伊集の花が咲く頃に仲間たちと「花見会」を開くように。その会が発展して2004年に「琉歌 伊集の会」が発足し、以来、20年に渡って毎月1回の定例会を開催しています。
上原さんが感じている琉歌の魅力は、「何かを感じた時に、すぐに残せること」。毎日詠むと決めているわけではなく、出会った風景はもちろん、日常の些細な出来事に触れた時に、「ふと、思いついたら詠む。たとえば、孫からの電話をもらったことから、〝敬老の日にや 孫からぬ電話 心励まされ 今日ん気張ら〟と詠んだり」。日記のような気軽さで、「心のビタミン」として楽しまれているそうです。

現在、60~80代の13名が参加する「琉歌 伊集の会」で事務局長を務めている上原仁吉さん

思いついた琉歌は、そのままパソコンに打ち込んで記録。
溜まったら歌集を発行されています
琉歌は、言葉を探す頭の体操
上原さんは「伊集の会」で会員さんたちの歌を推敲するほか、公民館でウチナーグチ(沖縄方言)の学習会も開いています。「学習会では、ヤマトグチ(標準語)をウチナーグチに直す宿題を出します。見た光景や自分の想いをヤマトグチでは言えるけれど、ウチナーグチだと表現できない人が多い。その勉強としていちばん良いのが琉歌。琉歌を詠むことは、自分が表現したい想いに当てはまる島言葉を見つける〝言葉探し〟なので、頭の体操にもなりますよ」と上原さん。
「時代の流れとともに、島の言葉が日常会話から消えてしまいましたが、琉歌を詠むと、誰かが三線を弾いて歌い出し、それに合わせてみんなが踊り出す。この素晴らしい沖縄の文化を未来に残していくために、私にできることを続けていきたいと思っています」。

「伊集富士」「地這い富士」という表現で多くの歌人に詠まれてきた上原さん宅の伊集。
自然発芽したものを40年余り育てたものだそう

伊集の会の歌集『琉歌の定期便 20号』(右)と、12号を数える上原さんの自詠歌集『歌の花筵』。
いずれも上原さんが編集、刊行しています

上原さんの妻の直子さんも「伊集の会」のメンバー。
後ろの琉歌はご夫婦揃って「琉歌大賞」に入賞した時のもの
花咲かす心 花生ける心 花愛でて孵でる 人ぬ心
花を咲かせる心、花を生ける心、花を愛でて心を清める、全て人間のみが持つ精神である。
花ぬ咲き清らさ 実ぬ成り清らさ 人ぬ肝清らさ 沖縄ぬ景色
花の咲く美しさ、果実が成る美しさ、そして人の心の美しさは沖縄の大切な風景である。
昨日ん今日ん明日ん 繰り返す中に 知らず積み上がる 人ぬ貴さ
毎日同じことを正しく繰り返すうちに、その人の徳は知らぬ間に積み上がるものである。
ただ歩で居てん 足跡や残る 乱れ無ん跡ゆ 残ち行かな
ただ歩くだけでも足跡は残る。乱れのないきれいな足跡を残して行きたいものである。
浮世さまざまに 人肝や変わる 欠きたい円だい 月ぬ御願
浮世が様変わりすれば人の心も変わる。欠けたり丸くなったりする月の願いも日々変わる。
いずれも、第11回「おきなわ文学賞 琉歌部門」で「一席 沖縄県知事賞」を受賞した上原さんの作品です